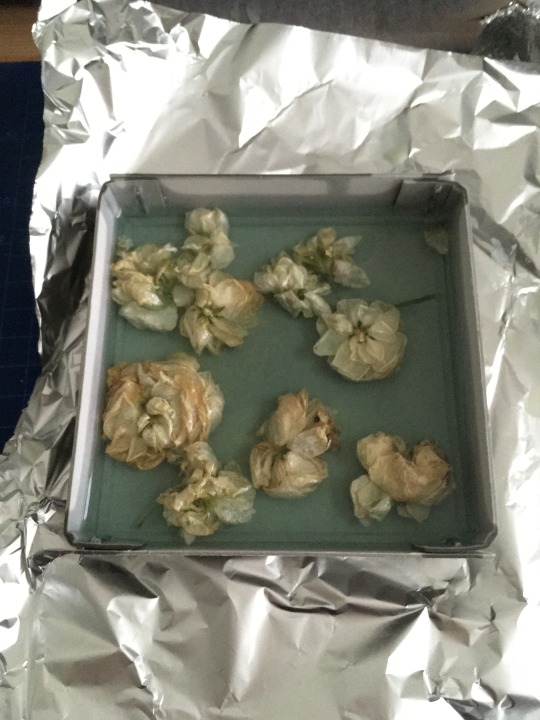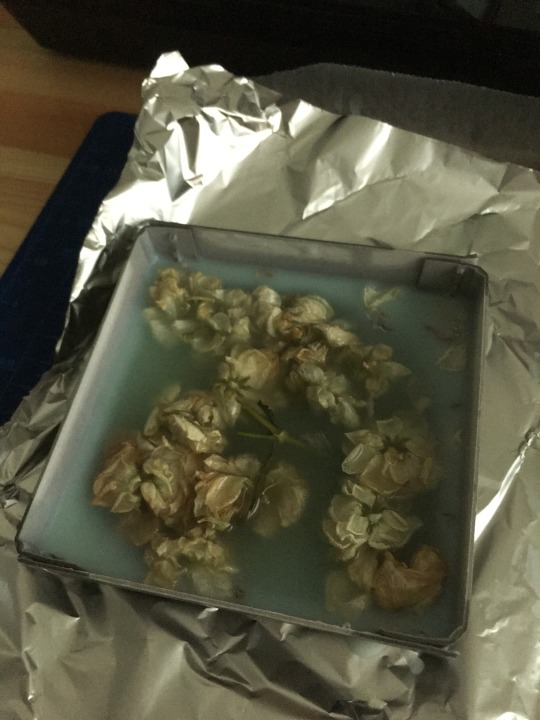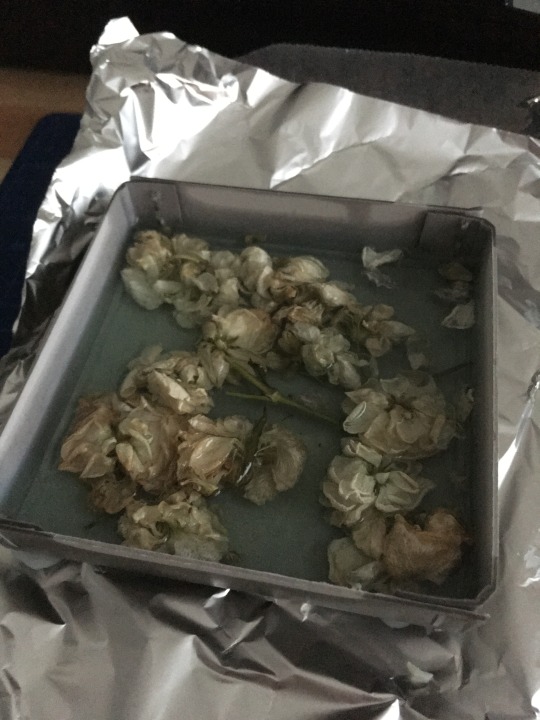Quote
「ああ、これでまた薪の暮らしを続けられるなあ」
積み上がった薪を見たときの弁造さんの健やかな表情を思い起こすと、胸の中は温かな物でいっぱいになり、そうか、そうなんだ、とひとつの気づきを得る。それは、暮らしへの弁造さんの深い感慨だ。生きることは、暮らすことなんだと。暮らすことは、寒い日にストーブを焚いて温まったり、今日一日頑張ったから乾杯するとか、そんなごくごくシンプルなもので埋めていくことだと、弁造さんのあのひとことが僕に語りかけるのだ。
奥山淳志『庭とエスキース』p. 184
0 notes
Quote
僕の目に映った弁造さんの“老い“とは、弁造さんという精神から離れていく肉体の姿だった。かつては背中合わせの一心同体であったはずの弁造さんの精神と肉体。でも僕の目の前にいる弁造さんの肉体は、持ち主の精神から遠くに離れようとしていた。この精神と肉体の距離によって生じるギャップこそが、僕たちが日頃呼んでいる“老い“の正体ではないか。弁造さんの姿はそんなことを感じさせた。
奥山淳志『庭とエスキース』p.166–67
0 notes
Quote
それは、「人間は外面的な幸福それ自体は吸収することができず、人間の心の中で『想像力』という酵素が作用することで初めて吸収できる状態になる」ということである。
つまり人間に幸福感を感じさせるものは、外見からも分かる「幸福な境遇」それ自体ではなく、むしろそれが種となって想像力に転化されたものであり、その「想像の中の幸福」を吸収することで人間は幸福を感じるのだというわけである。逆に言えば、外面的な豊かさをいくら与えられても、想像力という酵素が不足すれば豊かさの中で逆に窒息してしまうということである。
ここで言う「想像力」と言う概念は、可能性という概念をもその中で含んでいるが、いま述べたことも、想像力という概念を狭く解釈して可能性という言葉で置き換えると、もっとよく理解されるだろう。可能性とは、現在それがまだ実現していないからこそ可能性というのであって、それはその時点では想像の中にしか存在していない。しかしすべてを実際に手に入れて可能性が塗りつぶされ終わった状態よりも、まだ何も現実には手にしていないが可能性の中に莫大な資産が眠っている状態のほうが至福感に満ちていることは、多くの人が感じることである。
長沼伸一郎『現代経済学の直観的方法』p.426
0 notes
Quote
要するに実際に人間が何かを得て幸福感を覚える時というものは、ほとんどの場合その隣に「想像力」というものが影のごとく寄り添っているのであり、それが伴わない場合には外面的に何を与えられても人間は空虚感しか感じることがないのである。
そしてこれはひょっとしたら非常に大きな盲点だったのかもしれない。つまりこの「想像力」というものは、必ずしも文学的な美しい蜃気楼のようなものではなく、実は人間社会を支配する力学のかなり中枢部に位置するのであり、かなり大規模な拡張の余地を秘めているのではないか
長沼伸一郎『現代経済学の直観的方法』p. 425
0 notes
Quote
つまり、われわれはいままで、高度な文明とは大量のエネルギーや情報を使うことで、より大きく、より速く、より快適になることだと錯覚してきたのだが、むしろ真の「高い文明」とは、人間の長期的願望が短期的願望によって駆逐されるのをどう防ぎ、社会のコラプサー化をどうやって阻止するかという、その防壁の体型のことを意味していたのではないか、ということである。
長沼伸一郎『現代経済学の直観的方法』p. 405–06
0 notes
Quote
そういう「ばらばらに分けて解くことができる」という方法論こそが、いわゆる近代の「要素還元主義」なのだが、そういうことができるとなれば、先ほどの多様性の問題も簡単である。
つまり先ほどの話では、物事の乱立で生じた大量の相互作用の適正値を再計算するのが難しい、ということが重大なネックだったが、もし問題をばらばらに分解して解いていけるなら、それらの値は簡単に端から個別に求めていけるので、全体を共存させる方法もすぐに判明する。
要するにその方法論が使える限り、それらの命題は全て正しいことになるのだが、実はそれは例外的な特殊ケースで、一般にはそういうことは成り立たないのである。しかし近代は逆にその特殊ケースのほうが普通なのだと錯覚することで、「短期的願望をひたすら解放すれば、それが人間の長期的願望を極大化することになる」という強い思い込みを抱え込んでしまったのである。
つまり厳しい言い方をすると、米国のリベラル進歩主義は、単なる縮退を社会的進歩と勘違いしてしまったのであり、皮肉なことに近代以前の社会のほうが、短期的願望を人為的に抑え込む必要性をよく理解していたように思われる。
長沼伸一郎『現代経済学の直観的方法』p. 402
0 notes
Quote
インテグラルな現実へと格上げされる前の、意味の世界の直前にとどまるイメージを写真がもっともよく体現し、そのような直接性を持って出現し得るとすれば、それに対応するのは、おそらく、意味の病に犯される前の、いわば十分な輪郭を与えられる前の私たちの「準意識」であり「準身体」であると言うことができるかもしれない。そういう、存在が自意識を獲得する前の「震え」あるいは「揺らぎ」の水準での邂逅は、当然、隠喩的にではあるが主体の「死」を経験させるものであるだろうし、世界のあるがままの姿の顕現は、もしそれが可能だとすれば、そのような「死」と同時に到来するのでなければならないはずだ。
写真がこのような邂逅の可能性の地平において特権的な位置を占めるとすれば、それは、考えてみれば、バルトの言うように、写真という媒体の特質に、深く「死」が刻印されているということに関わるに違いない。写真が私たちをもっとも深く撃ち、私たちの主体性を揺るがす瞬間とは、現在の意味の体系の中で写真を価値づけるということ以前に、写真に写された光景が、今はもうすでにないという決定的な消滅の事実、そしてその消滅したはずのものがまざまざと眼前にあるという奇妙さが突然のようにして私たちを襲う瞬間である。私たちは、普段、この絶対的な落差ーー過去の「存在」の事実性と現在の「不在」の事実性の間にぽっかりと口を開ける存在論的な深淵ーーを殆ど意識しないで済んでいるのだが、それが、何かの拍子に襲いかかってくる。そこで出会う「死」の感覚とは、認識の対象としての死ではなく、どこまでも認識の枠組みを超える得たいの知れないもの、しかし恣意的な想像とは程遠い絶対的な「現実性」を持ったものとしての、つまりは表象不可能なものが、にもかかわらずそこに厳然として「在る」という感触としての「死」である。
バルトは、そのようなプンクトゥムの経験を、写真の内部に発見できる特定の細部の効果と結びつけて語ったが、問題は、因果関係にあるのではない。起因となるものが、彼の言うように写されたものの細部である必要もおそらくはない。何が契機であれ、写真の経験のプンクトゥム的瞬間には、与えられた写真が、それ自体はかつて在った世界の断片に過ぎないのに、その断片とともに、失われた世界の存在が、その不在性にも抗して、まるで一挙に全体的なスケールで回帰するという驚きがつきまとっている。この断片から全体への飛躍こそが、驚愕をもたらすのだ。
林道郎『死者とともに生きるーーボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す』p. 137–38
0 notes
Quote
ヴァーチャル性は幸福の代用となる陶酔の形式だが、それが幸福に近づくのは、幸福からあらゆる参照項をこっそり抜きとってしまうという理由によってでしかない。ヴァーチャル性はあなたにすべてを与えるが、同時にあなたからすべてを巧みにかすめとる。主体はそこでいわば完全に実現されるのだが、主体がかんぜんに実現された��き、それは自動的に客体となる。
林道郎『死者とともに生きるーーボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す』p. 127–28
0 notes
Quote
「差異」という概念は、ボードリヤールの思想空間においては、強度そのものではなく、そのシミュラークルに過ぎず、同一構造を延命させるためのゲームに内在する要素に過ぎない/〜/私たち個々人は、「差異」の生産者として、世界を成立させている同一平面上に自らを登録することによって、存在の権利を得るというわけだ。
SMAPの楽曲「世界に一つだけの花」は、そういうボードリヤール的視点から見ると、疎外された自分を解放するための肯定の歌であるどころか、その意味するところは真逆で、「君はかけがえのない差異の体現者でなければならない」という、近代以降の資本主義社会における定言命法の反語的な表現ということになるだろう。それは解放などではなく、システムからやってくる差異化への要請であり、「個性」という牢獄への疎外なのだ。差異として自己登録しなければ、人間主体は、世界という平面上で交換可能な記号になることができない。つまり、もはや差異的な存在であることを望まないわけにはいかないのだ。登録への欲望を放棄することは許されないのだ。
林道郎『死者とともに生きるーーボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す』p. 120
0 notes
Quote
六八年五月の運動の中で自然発生的にあちこちに出現した落書きや、七〇年代前半、ニューヨークの地下鉄や街路に突然増殖を始めたグラフィティなどを、シミュレートされた一般経済的なコミュニケーションの回路を逸脱し、機能不全に陥らせる「テロリズム」として捉えています。そうして回復される、意味に交換することが不可能な、空虚な、しかし過剰な物質性を帯びた徴の匿名的かつ儀式的な交換の連鎖を彼は、一般的な等価交換の論理では理解できない過剰な(あるいは余計者としての)「象徴交換」と捉えるんですが、その考え方のもとには、マルセル・モースの贈与論とかジョルジュ・バタイユの蕩尽論などがあります。文化人類学におけるポトラッチ概念に典型的に見てとれるのですが、自らを滅ぼしてしまうほどにエスカレートしていく(不等価)交換への熱情に人間の原初的な関係の形を探り
そこに、シミュレートされた等価交換のサイクルを裏切り、経済的なロジックに収まらないコミュニケーションの可能性を見ようとしているんですね。ある意味で、「死」の問題もその延長上に位置づけることができます。
林道郎『死者とともに生きる ボードリヤール『象徴交換と死』を読み直す』
0 notes